最近、とても衝撃的な育児書を読みました。
なんと、子供のわがままな感情をコントロールできる(かもしれない)方法が掲載されていたのです。
本を読むだけでは私の脳みそに定着してくれないので、整理も兼ねてこの場で私流にアウトプットさせていただきます。
我が子のわがままにお悩みの皆さまと共有できれば幸いです。
子供の感情を読み取る力を育むためには
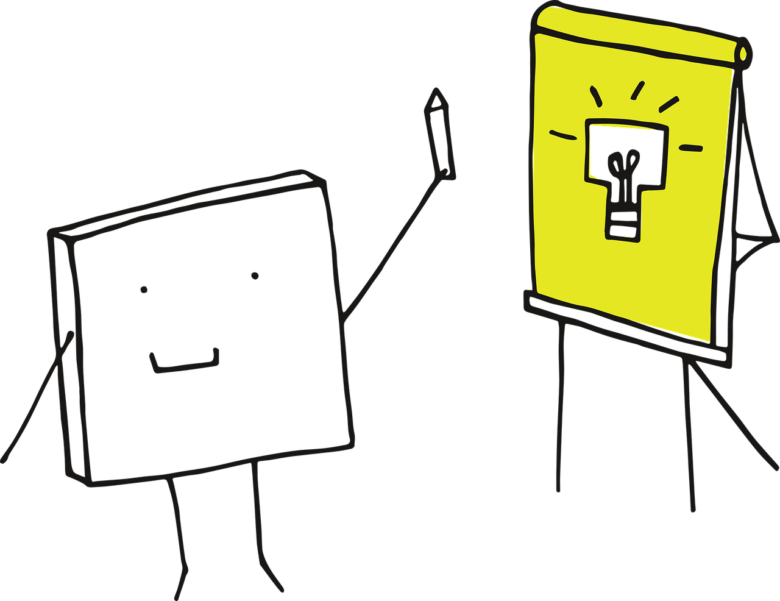
子供と感情について会話していると
「他人の感情を理解し他人を気づかう力、つまり共感力や思いやりが高まる」と言われています。
そのやり方についてはこの本にしっかりと書かれています。
ただ、翻訳本なので若干わかりづらい面も・・・。
我が家の実例を踏まえて、私なりに解釈した方法をお伝えします。
1.感情を言葉で表す練習をする
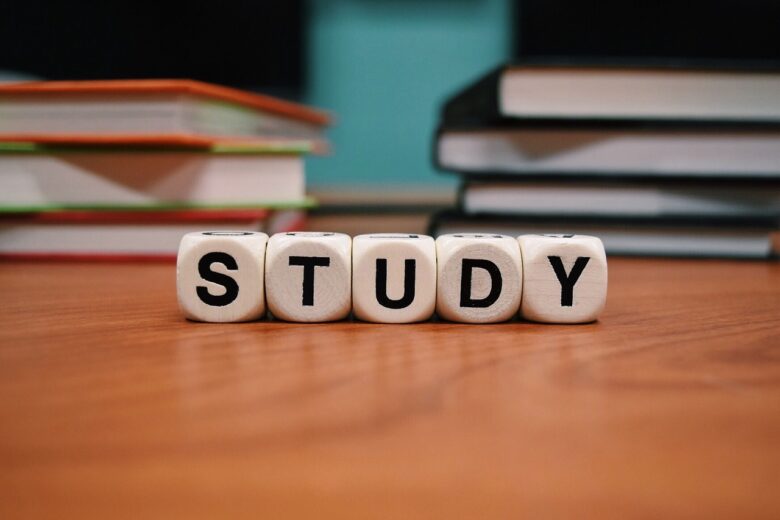
まず、自分の感情を話し、子供の感情についても尋ねます。
例えば、こんな風に。
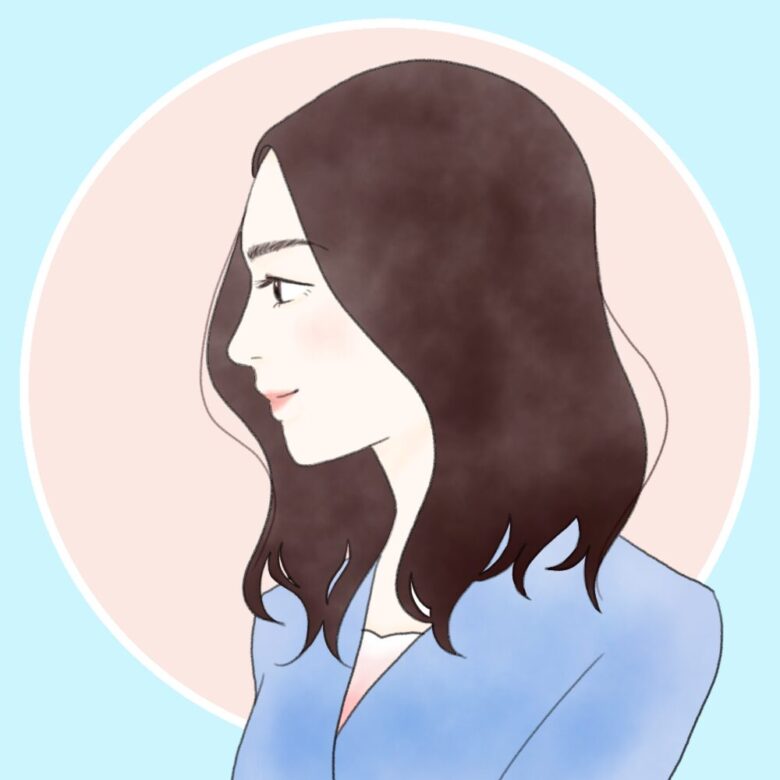
今日は仕事で嫌なことがあってイライラしてるの。
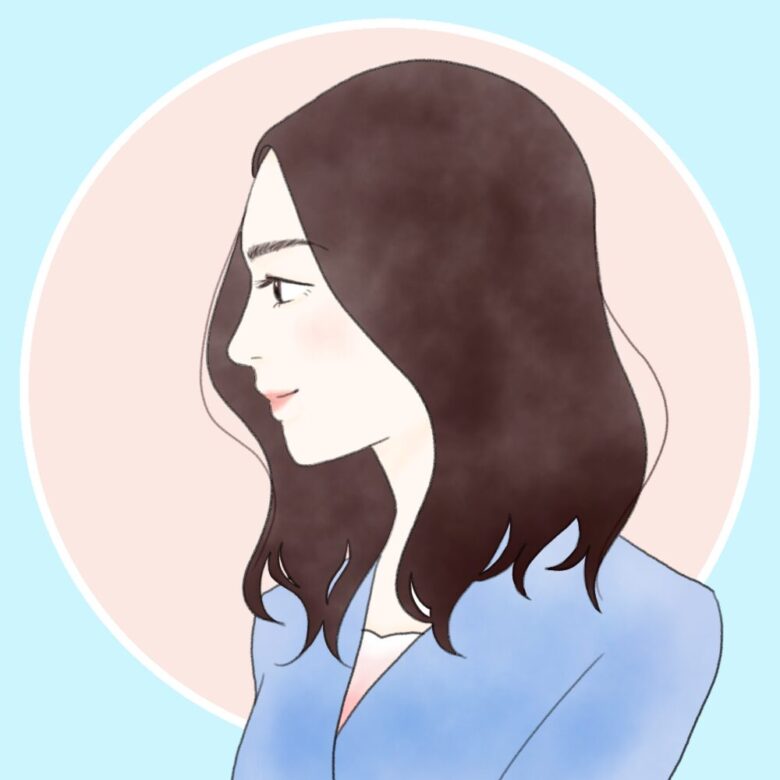
少し悲しそうな顔をしてるけど、大丈夫?
こうした会話を繰り返すことで「他人の感情を理解する」「他人を気づかえる」能力が養えるようです。
私は限界まで無理をしてる自分に気づかず、ささいなきっかけで臨界点を超えてしまい爆発することが多々あります。
家事・育児がとても苦手なので・・・。
ただ、子供と同居している以上、最低限のタスクをこなす必要があるので、自分の感情を伝えるように心がけています。
(毎日つかれたと話す母親ってどうなのかなぁ・・とも思うのですが、それが正直な自分の姿なので)
「今日は献立を考えながら買い物して頭が疲れた。」
「雨で洗濯物が濡れて悲しかった、余計な家事が増えて疲れた。」
「雨の中たくさん歩いて疲れ果てた。」
そして、最後にこう伝えてます。
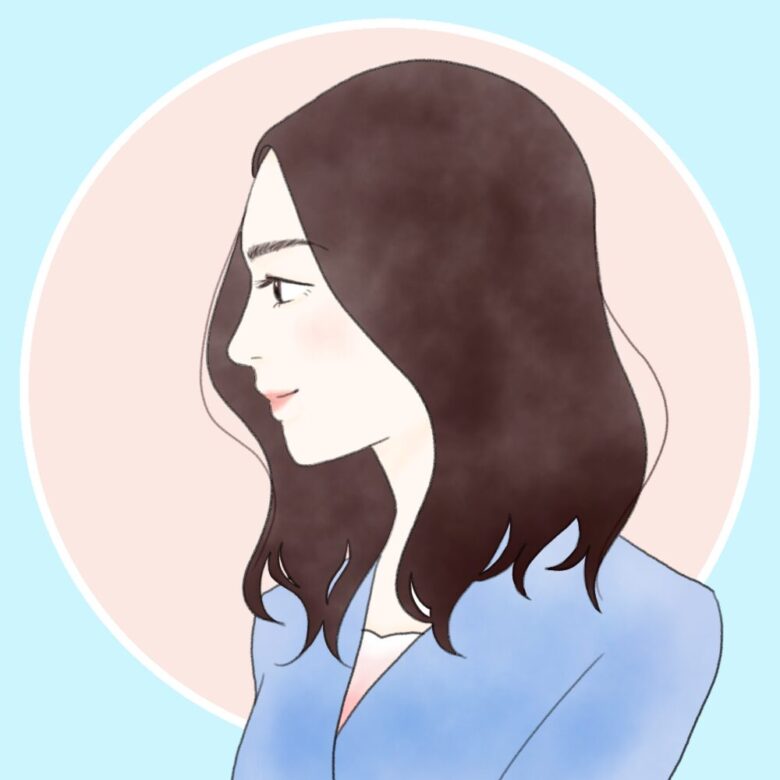
だから、あなたとは今日は遊べない。
or
だから、今日は少ししか遊べない。
ちなみに、生成AIに「しんどい」のバリエーションを尋ねると、次の答えが出てきました。
- つらい
- 苦しい
- 悲しい
- 負担がある
- 疲れる
- 厳しい
- 疲れ果てる
- 気が重い
- 疲れがたまる
- 疲れきった
夫以上にわかってくれない子供にイライラしないため、自分の感情とも向き合っています。
2.子供の言動が他人にどう影響するかを親が教える

子供をしつける時に、感情について触れるようにします。
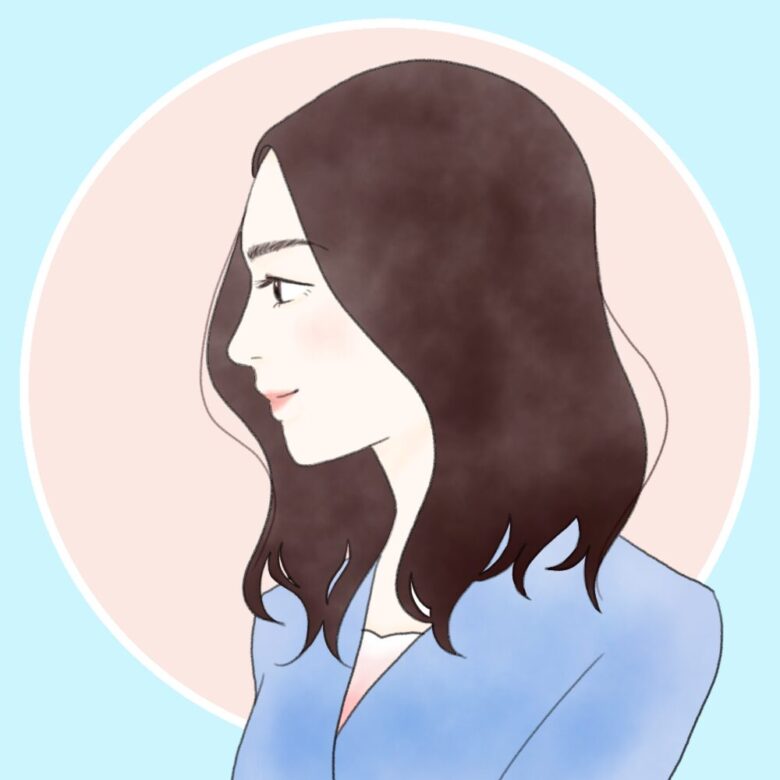
今日はおもちゃを散らかさないで。ママはしんどくて片付けを手伝えないから。
子供の言動が他人にどう影響するかを親が説明すると、他人の感情を想像し、自分にも責任があると考える力がつくそうです。
我が家は娘とパパの仲が悪く週末はぎゃーぎゃーわめき声が絶えません。
そこで、子供の言動を責めるのではなく、大好きなママ(私)がどう感じているかを伝えるようにしています。(いい年した大人(パパ)をしつけることは私にはできないので、ノータッチです)
「嫌な思いをしているのはわかるけど、大声でわめかれたらママは頭が痛くなる」
「ママはあなたのわめき声を聞くのはもううんざり。この家で過ごすことができなくなる」
等々。
実際、次のような研究結果も出ています。
子供の言動が他人にどう影響するかを親が説明していた子供は、
- 罰を与えるなどの力でねじふせられていた子供よりも、共感力が高かった
- そうでない子供よりも、過ちをつぐなおうとしたり、困っている人を助けようとした
3.子供の気持ちを受け止めて感情をコントロールさせる
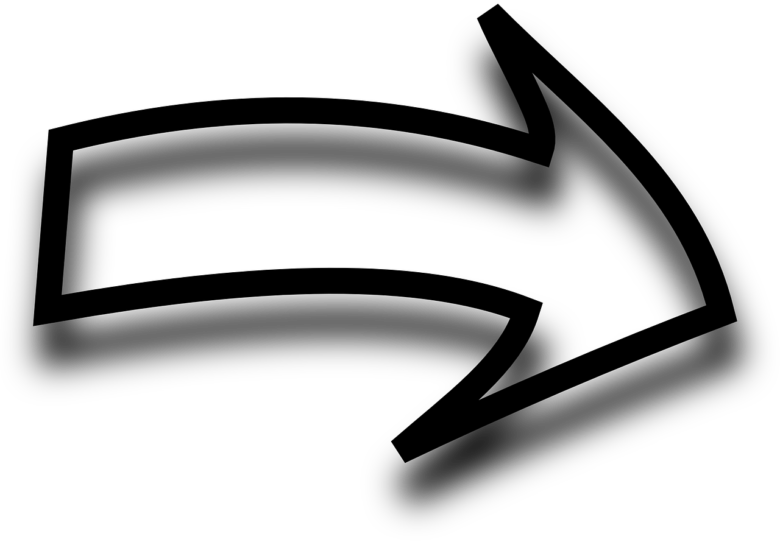
親の目には大げさだったり筋が通っていないようにみえても、子供の感情に寄り添うことが大切です。
細やかな対応を示すことで、子供は親に対して安心・安全を求め、頼ることができると学習し、心の回復力や柔軟性の高い人間に育つことができます。
3-1.子供の気持ちを受け止める
子供が機嫌を損ねると「静かにしなさい」と言いたくなるものですが、専門家によると、子供の感情に寄り添い、受け止めるのが最善のアプローチだそうです。
我が家では子供の寝起きが最悪で、ママが隣にいないと結構な割合でわめきちらしています。
ママが来てくれるとご機嫌になるのですが、手が離せない・離したくないときはどうしようもできません。
そんな時は「ママが隣にいなくて寂しかったんだね。」と伝えるよう心がけてます。
このように、機嫌を損ねたときに親が反応を示すと、子供は自分の感情に対処する力が高まり、他人が怒ったり泣いたりしたときに手助けをするなど、思いやりのある言動をとる傾向があるそうです。
3-2.感情をコントロールする方法をアドバイスする
子供の気持ちを受け止めた後は、機嫌を直してもらうことが必要です。
例えば、娘の場合「部屋ではわめいてもいいけど、ママと何度も呼ばないで欲しい。」と伝えています。
「ママ、ママ、ママ・・・~~~」と連呼されても困るので。
また、別のタイミングでは不機嫌になった時に壁を蹴っていたので、
「壁に穴があくと困るから床を蹴るようにして」と伝えました。
困った状況を乗り越えたり機嫌を直す方法を親がアドバイスすると、子供は思いやりを身に着けられるそうです。
4.こどもに親の要望を伝える

親は子供に対して「この場面ではこんな言動を取ってほしい」と考えています。
けれども、それをはっきりと言葉にして子供に伝えている親はどれ程いるのでしょうか。
親戚と対面するとき
「礼儀正しくふるまい、何か聞かれたら答え、相手の目を見て話をすべきだ」
ということ位、我が子がわかっていると思い込みたいですが、現実はそう上手くはいきません。
「初めて会う大人と接する方法」は事前に何度教えたとしても、子供には伝わっていません。
習い事をはじめるにあたってオリエンテーションがありました。
事前に伝えられていた情報は次の通り
- 所要時間は1時間程
- 保護者だけの参加で大丈夫
その場に、明らかに未就学とわかる子供がいました。
初めのうちは本を読んでおとなしくしたたのですが、30分を過ぎたあたりから段々、じっとしていない、歩き回る、先生の説明の邪魔をする、等の行動が勃発。
他の保護者や先生は華麗にスルーしていましたが、ついに問題の母親がひと言
「恥ずかしいからやめてちょうだい」
・・・
子供は恥ずかしくないので、要望は聞き入れられませんでした。
子供に要望を伝えるときは、「なぜ」そうして欲しいのかを伝えると効果的です。
例えば「ブロックを片づけて」だけで済ませず、
「ブロックを片づけて。誰かが踏んだら痛いからね。」のように伝えるのがコツです。
「〇〇を片づけて」と伝えると
「これやった後でもいい?」「寝る前でもいい?」と言うようになってきた娘。
緊急性が低い場合は後の片付けでも良しとしていますが、すぐ対応して欲しい場合は「なぜ」片づけて欲しいのかを伝えています。
その他、我が家では次のように対応しています。
「(キッズ)カメラは床に置かない方がいいよ。踏むと壊れるからね。」
「はさみを使い終わったら閉じてね。開いたままだとケガするかもしれないからね。」
子供がルールを破った場合は、ルールを再確認し、反省点を話し合い、改善策を一緒に考えます。
ホント、子育てって大変!!
最後.やさしさ・思いやりの手本を示す
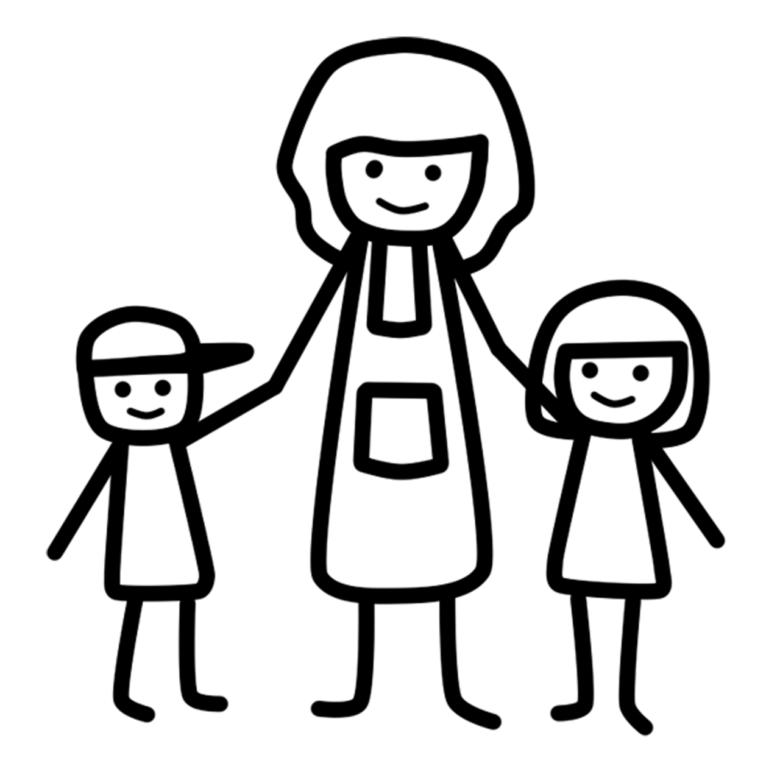
誰しもわかっていることですが、やさしさ・思いやりの実践は難しいです。
私も子供と自分の親にしかやさしさを発揮できていません。
夫に対しては「チクチク嫌味」「子供の前で不満たらたら」が止まりません。
アンガーマネージメントを少し勉強したこともありましたが、知識が身に付いても実践できませんでした。
ということで、不満たらたらを止めた時のメリットと、止めれなかった時のデメリットを考えてみました。
子供は親の背中を見ています。
私が家人に敬意を払うようになれば、私や学校の先生だけではなく、様々な人に思いやりを示すようになるかもしれません。
子供は親の背中を見ています。
私が家人に敬意を払わない場合、子供がそれを真似、いずれ私や学校の先生に不敬な態度をとるようになるでしょう。絶対に。
・・・
子供のためにも、態度を改める必要がありそうですね。
完璧な人間はいない
現実問題として、いつも人にやさしくするのは難しいです。
いけないと思いつつ、子供に対してカッとなったらどうしたらよいのでしょう。
謝るだけで大丈夫です。
どんなにくだらなくても理由と一緒に伝えるとより効果的でしょう。
この本で、どんなにくだらなくても理由を伝える重要性を知ることができました。
今までは「怒りすぎちゃってゴメンね。」で終わらせていましたが、この本を読んでからは
「怒りすぎちゃってゴメンね。洗い物で疲れちゃってイライラしてたの。」と伝えるようにしています。
正直、子供に自分の失態を伝えるのは恥ずかしかったのですが、それも次第に慣れてきました。
子育てすることで、自分の成長も感じています。



コメント